私は小学生の頃から、「塾」に通っていました。
2〜4年生くらいまではワケも分からず(今も健在の)大手進学塾「中学受験」クラスに在籍。
モチベーションの低さに(わたしって中学受験しないよね…?)と気づき
5年生で普通のクラスに切り替え、そこから中学2年生まで通い続け
あまりにも成績が伸びないので個人塾に変えました。
名もなき小さな塾でしたがとても面倒見のいい先生達でしたので
たちまちやる気が上がって、中3の内申がぐっとあがり学力もアップ。
高校、大学と志望する学校に合格することができました。
そもそもどこまで塾が必要だったのかと考える
私の場合の話をします。あくまでこんな人もいるよ、と参考までに。
大手進学塾に6年間在籍
母親は、私が小さい頃から「習いたい」と言った習い事を我慢させずに習わせてくれました。
進研ゼミを少々かじったことはありますが、正直続かない。
付録がいっぱい、山のように積み上がる教材は手もつけないまますぐに辞めることになりました。
おそらく、何となく「塾に通いたい」と言い出した小学校低学年の私に
期待の意味をこめて投資したのでしょう。
小学校の成績はそこそこ良かった記憶がありますが
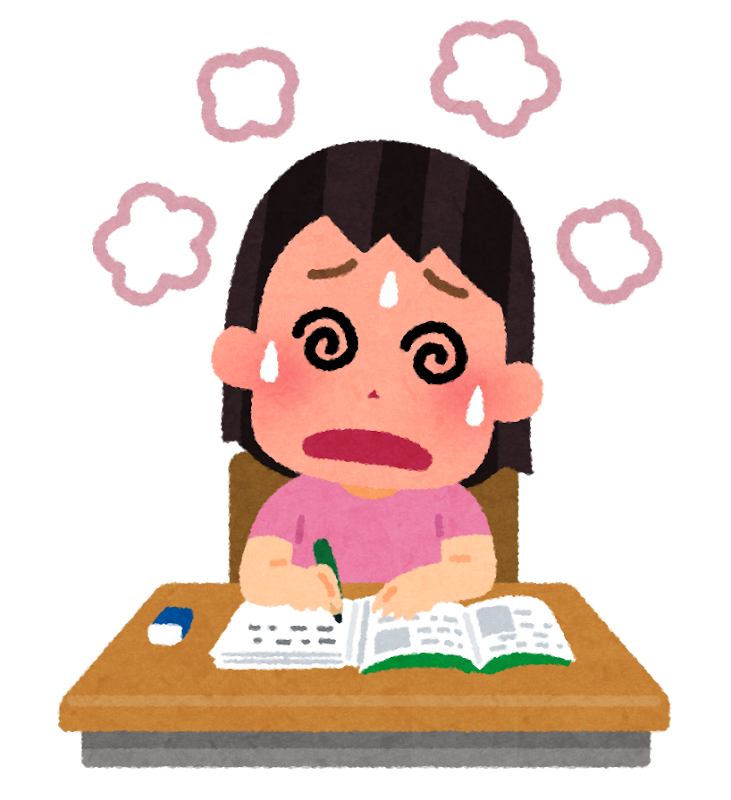
目的もよくわからないまま「何となく」続けていたので
中学受験クラスの中ではジワジワと落ちこぼれていき
こども心にしんどかったイメージです。
高校受験に目的を切り替えた後も、そもそも塾に通う意味なんて
自分自身がはっきりさせずに通っていましたから
成績が目に見えて伸びた!ということもありませんでした。
しかも中学から部活が始まり、夜から始まる授業は
とてもじゃないけど体力が残っていなくて、居眠りばかり。
働いていた母がギリギリ届けてくれるお弁当を休み時間に食べて再び授業。
寝る時間も遅くなって朝はいつもダラダラ、学校の授業も眠くて成績はイマイチ。
大手から小さな個人塾に変えてみた
中2の終わりに、学年で頭が良くて有名な男の子たちが通う個人塾の噂を聞き、真似して入塾。
1授業10人程度の小さな塾でしたが、とても親しみやすい先生達と気の合う仲間。
主体性を持った学習姿勢と、気軽に質問できる雰囲気も相まって、学校の内申がうなぎのぼり!
中3でグンと伸びた私は、志望する高校に推薦入学することが出来ました。
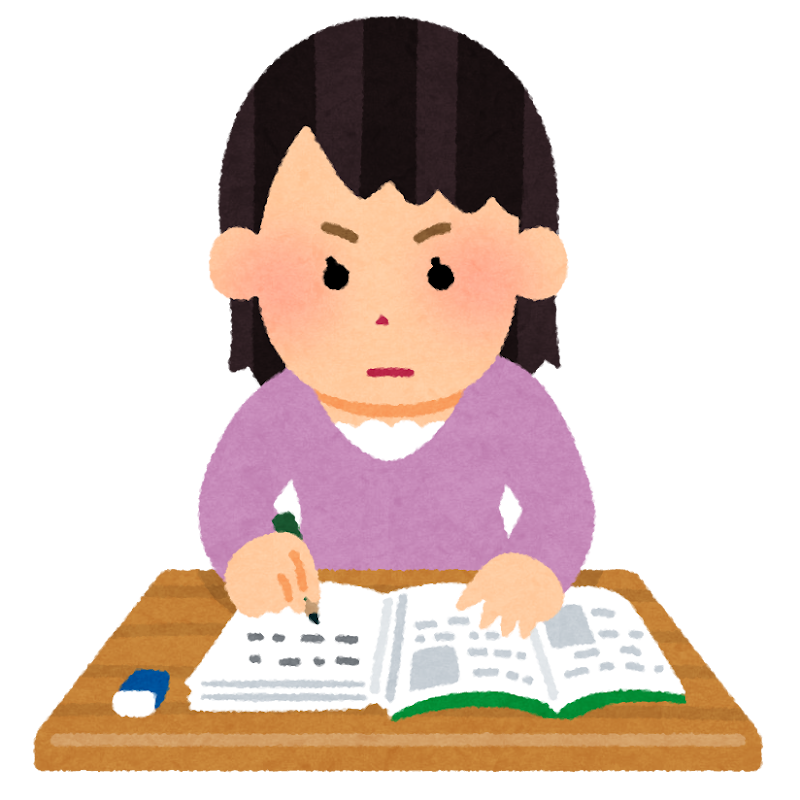
このときの経験から
「有名な塾に通う=必ず成績が上がるわけではない」
ということを身を持って実感しています。
私にとって塾は何だったのか
本当に意味があったと、今でも感じるのは中3で通った個人塾。
残りの塾人生は一言、「眠かった」としか言えないのです…ごめんよ、母さん(泣)
主体性のない、目的がはっきりしない、モチベーションの低い、疲れている子どもたちには
塾の一方的な授業は苦行以外の何物でもないと、わたしはしみじみ思います。
塾は、子どもが心の底から「変わりたい」「成績を伸ばしたい」と湧き出る情熱を持って
初めて功を奏すのかもしれません。
塾に行ったほうがいいかもしれない子の特徴
しかし、親が担えない役割を、第三者に任せるという考え方があることも
忘れてはいけません。
共働きが大半の社会において、親が付きっきりで子どもに勉強を教えるということは
あまりにも高い理想であり、非現実的でもあります。我が家も無理〜。
そこで、塾通いに向いている子どもの特徴を挙げてみます。
1.家庭での学習習慣が身についていない子
- 自分から進んで勉強しない
- 家でやろうとしても気が散ってしまう
→塾という「強制力がある」場で、一定時間集中して学習できるようになる
2.親が勉強を教えるのに限界を感じている家庭
- 教え方が分からない、時間が取れない
- 親子で取り組むとケンカになりがち
→第三者(先生)に任せることで、スムーズに学習できる
3.学校の勉強が簡単すぎて退屈そうにしている子
- もっと上のレベルに挑戦したい気持ちがある
→中学受験や先取り学習を見据えた塾が向いている
4.「競争」や「周囲からの刺激」でやる気が出るタイプ
- 周りと比べられてモチベーションがあがる
→塾ではクラスメイトの存在が刺激になって、やる気アップにつながる
5.目標(中学受験・成績アップ)がはっきりしている子
- 「〇〇中に行きたい」「テストで◯点取りたい」など
→塾での計画的な指導で、目標に近づきやすくなる
6.家では甘えが出やすい子
- 「やらないとだめ」と言われても、のらりくらりしてしまう
→外部の先生には自然と「しっかりやろう」という姿勢になることも
私自身の経験が、塾に対する価値観の土台となっているため
子どもたちには情熱を持って「こうなりたいから塾に行きたい!!」と申し出があるまでは
塾に通わせるつもりはありません。
中学受験を目指すのなら、話は全く別ですが
我が家にその予定はありませんし、特別裕福な家庭でもないですし
3人の教育費にお金をかけすぎて、家族の娯楽費を削るとかそういうのは避けたいので
中学は公立、受験は高校からで十分だと思っています。
そして高校受験を目指すのなら、小学生のうちは家庭学習、そして自学習を
とことん身につけるように心がけています。
我が家の場合
通信教育が家庭学習に功を奏す
家庭学習の習慣を身につけるために
我が家では3人共に幼稚園の頃から「スマイルゼミ」を続けさせています。

姉に関しては年長さんからやっているので6年目!
さすが6年目ともなると、毎日タブレットを開くのが習慣となり
朝起きて5分とか、学校に行く前に玄関で5分とか
夕飯後に20分とか、移動の車中で10分、寝る前に5分とか。
とにかく、いつもなるべくそばに置くようにして
出かけるときには、たとえやらないとしても持っていくようにして
ご褒美ゲームでもいいから、タブレットを開く習慣を身に着けさせました。
隙間で学習するのが日課となり、それを6年も続けたとなるとこれはもはや生活の一部。
5年生のうちに漢検7級、英検5級の取得を目標としています。
学研に行き始めた双子
一方、双子はというと…
ケンカが毎日勃発するようになりまして。
スマイルゼミもやったりやらなかったり、姉ほどうまくいかず
「もう無理〜だれか助けて(泣)」とすがる思い。
基礎学力を上げる目的で、夏休みから学研教室(国語算数)に通わせ始めました。
2教科で9000円くらい。
双子が通う学研教室の先生が、偶然双子ママということもあって
二人をとても良く面倒みてくれています。
自分の好きな時間に行き、終われば帰れる=終わらないと帰れない
全ては自分次第、頑張れば表彰される!主体性の持ちやすい環境です。
ガチガチの縛り(時間的、宿題量等)がないので
双子にとっては負担感が大きくなく、宿題もそこそこしっかりやって週2回通っています。
なんなら余った時間で学校の宿題とか持ってってやっていたりします。
まだまだ声掛けが必要ですが、少しずつ自学習が定着する初めの一歩を踏み出せた様子です。

その様子を見ていた負けず嫌いな姉がなんと「私も学研いきたい」と言い出しまして。
まぁ姉のことだからしっかりやってくれるだろうと期待しつつ
今ではケンカしながらも仲良く3人で通っています。
理想はお金をなるべくかけずに賢くなってもらうこと(笑)
30年前の自分の時代には、スマホもパソコンも当然なくて
勉強は塾で教えてもらうことが普通の概念でしたが
今の時代には、基本家にいても何でも揃ってしまいます。
インターネットがあれば欲しい情報が手に入り、YouTubeを開けば無料で学習動画が見れて
オンラインで授業を受けることも出来れば、タブレットで通信教育も受けられる。

なんて便利な世の中なんだろう、私がもし人生2週目をしたら
なるべくお金をかけずに、使えるものを駆使しまくって、賢くなっちゃうんだろうな〜とさえ思ってしまう。
それくらい、便利なもので溢れかえってる。
羨ましいです、今の子どもたち。
あの居眠りばかりこいてた学生時代の睡眠時間、今の時代だったら取り戻せるかな〜なんて(笑)
以前、「塾に行きたい」と何度か行ってきた娘にその都度返しました。
「なんのために行きたいのか説明できる?」と。
目的がはっきりしない塾通いははっきり言って無駄です。
ましてや通う本人が理解していなければ捨て銭。
それなら家族で旅行に行って楽しい思い出を作ったほうが有意義、私はそう思うのです。
何のために行きたいのかと問われて答えられなかった娘は
そのうち行きたいとは言わなくなりました。
理由は「みんなが通っているから私も行きたい」だったからです。
そのみんなとは”中学受験組”、そもそも方向性が違うのですから真似しなくてよろしいかと。
きっぱり諦めた娘は大好きなテニスに打ち込むべく、家庭学習にいそしむようになりました。
双子はまだまだ発展途上ですが、いつか姉のように自学習が定着化してくれることを祈っています。
結局のところ、家庭の学習方針は親の考え方次第が大きく左右するものではありますが
少なくとも私は、地頭の良い、自学習が定着している子どもにすべく
当分はスマイルゼミと学研の二刀流で攻めていきたいと思います。
※我が家の場合のお話ですので、参考程度に。




コメント