ここ数年で子どもたちの「発達」に注目が多く寄せられるようになったのと同時に保護者の関心も高まり
「言葉がでない」「集団に入りづらい」「療育に通わせたい」と相談にくるママさんがとても多いです。
発達障害は昔より増えたのか?それとも社会の意識が高まったのか?
そしてそれに伴い現場にはどんな課題があるのか。
この問題に日々直面する者として、ちょっと真面目な話、そのあたり少し掘り下げてみようと思います。
発達障害が、”増えた”というより”気づく”ようになった
診断基準が広がった
昔は「ちょっと変わってる子」「落ち着きのない子」で済まされていた子どもたちが
今は「ADHD」や「ASD(自閉スペクトラム症)」などと診断されるようになりました。
つまり、今のほうが“診断されやすくなった”のです。
それゆえに「グレーゾーン」と呼ばれる子どもたちが増えたのも事実です。
関心が高まり、理解と支援が進んできた
教育現場や医療現場でも発達障害に関する知識が広まり
保護者や先生が「これって…発達の特性かも?」なんて気づく機会が増えてきました。
“気づかれやすくなった”というのも大きな理由の1つのようです。
メディアやSNSを通じて情報が広まり、発達障害が珍しくなくなったのと同時に
保護者が早く気づき、早期に行動する保護者が増えているのです。
実際、早い子で2歳頃から発達の相談をしにくるママが多いように思います。
支援につなげる意識が高まっていて、結果として相談件数も増加しているということ。
発達障害の実態と増加のデータ
通常学級における発達障害の可能性がある児童生徒数の割合:8.8%
2022年の文部科学省の調査で、通常の学級に在籍する小中学生8.8%に
学習や行動に困難のある発達障害の可能性があることが分かりました。
2012年の調査6.5%から2.3ポイント増え、35人学級であれば3人ほどの割合となります。
特別支援学級に在籍する児童生徒数の増加:10年で10倍
文部科学省のデータによると、上記の生徒数は2006年の約7000人から
2019年には約7万人へと、10年余りで約10倍に増加しています。
背景に、発達障害者支援法の施行や、発達障害に対する認知度が上がってきたことがあるようです。
発達障害の診断率の国際的な増加傾向
米国疾病予防管理センター(CDC)の報告によると
自閉スペクトラム症(ASD)の診断率は1975年には5000人に1人だったのが
現在では36人に1人と推定されているようです。
本当に増えている可能性もゼロではない?
環境要因(妊娠中のストレス、高齢出産、低体重・早産児、化学物質など)によって
発達障害のリスクがわずかに増える可能性があるという研究もあるようですが
これは「急激に増えた」と言えるほどの変化ではないとされています。
現場のリアル
乳幼児健診や園・学校現場での気付きがふえたことにより、早期相談が増加していますが
それに伴い、医療・教育・福祉など支援の現場は深刻な状態にあります。
人員不足と長い待機期間
専門職(小児科医、児童精神科医、臨床心理士、作業療法士、言語聴覚士など)の絶対数が足りていません。
実際、児童精神を専門とするクリニックは初診受付をお断りしていたり、受け付けても半年待ちなんてザラにあります。
療育の需要増と対応の限界
療育センターや発達支援事業所には申込みが殺到し、空きがない・キャンセル待ちが続くという状態です。
療育の重要性が周知される一方で、質の確保や継続的な支援が困難になってきているのも事実です。

施設は増えてきたけども、必要とする子どもも増えて、追いつかないことも…
→支援の「量」と「質」のバランスを取るのが難しくなっている現状です。
教育現場の負担増加
通常学級に在籍する発達特性のある児童(いわゆるグレーゾーンの子)が増え、担任の負担が増加。
特別支援学級の枠も足りず、加配教員や支援員が不足。
保護者からの要望に応えきれず、教員の疲弊が深刻化しているという現状があるようです。
医療・福祉との連携不足
教育・医療・福祉が連携して支援するのが理想ではありますが
実際は情報共有の仕組みや時間的・人的リソースの不足により、スムーズな連携が難しい地域も多いです。
私の知る限りでは、自分の住む自治体の対応に絶望し、転居を検討するお母さんもいました。

相談してくれても、なかなか次に進めないもどかしさに、私も胸が痛みます
時間がかかっても、一緒に前に進んでいく
今、この子にできることは何か、それと同じくらいママの不安な気持ちもしっかりと受け止めつつ
必要とする支援を必要なときに受けられる社会にするためには
医療・福祉・教育の横のつながりをもっと大切にしていく必要があると感じます。
時間がかかっても「この子にはこんな関わり方をしていくといいかもね」と
家庭でできることを伝えられるよう、私も日々勉強中です。







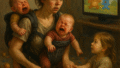
コメント