「うちも、そろそろスマホかなぁ・・・」
小学校高学年にもなると、そんな空気がじわじわ漂いはじめますよね。
「◯◯ちゃんがスマホ持ってるから私も欲しい!!」
よくある光景だと思います。
習い事の連絡、友達とのやり取り・・・
親世代の小学生時代にはなかった世界が、子どもたちには広がっています。
連絡網もなくなったし、そもそも固定電話のあるご家庭がどれだけあるだろうか。
スマホ、何歳から持たせる?
今や、小学生からi-phoneを持っている子どもが少なくありません。
かたや、「うちは中学生までスマホ絶対になし!!」とがんばるご家庭もあります。
・・・で、結局、何歳から持たせるのが正解なの??

今、この子にスマホを持たせて本当に大丈夫なのかなぁ?
この問い、実は答えがないみたいなんです。
時代も、子どもも、家庭も、すべて違う。
だからこそ、「我が家にとっての正解」を探していくしかないのです。
言い換えれば、隣のご家庭の正解がうちに当てはまるわけではないということ。
これって結構難易度高め?
私達が子どもの頃にはなかった悩みです…
我が家の場合
我が家では、かつて共用として置いておいた家用のスマホ(電話、LINEあり)を
今お姉ちゃん専用のスマホとして使っています。
たしかそうなったのは・・・4年生を過ぎてからだったと記憶しています。
学童を卒業して行動範囲が広がったのがきっかけでした。
本人がスマホの使用を強く希望したというよりも
私が持たせたほうが安心できたから、というのが大きく占めています。
世間一般はどうしてるのだろうか
世の中の流れを見てみると・・・
- 世界では13歳以上が推奨されている(SNSの利用規約もここから)
- 日本では「中学入学」で持たせる家庭が急増
- とはいえ、小4・小5くらいからスマホ持ちがじわじわ増えてきている
特に、小5・小6で「連絡用に」スマホを持つケースが増えています。
塾や習い事の行き帰り、一人で移動する機会が増えるタイミングですね。

とはいえ、「みんな持ってるから」という理由だけで焦る必要はありません。
大切なのは
「この子にスマホが必要か?」「持ったあと、ちゃんと使いこなせるか?」
ここを見極めることが大切です。
年齢より「使う力」が大事
スマホは、ただ便利なだけの道具ではありません。
楽しいこともたくさんある反面
SNSトラブル、依存、知らない人との接触―――
小さな画面の向こうには、子どもにとってまだまだ未知の世界が広がっています。
年齢だけで判断するのではなく、その子が「スマホを使う力」をどれだけ備えているかがポイント。
スマホを持つメリットもちゃんとある
持つメリット、実はたくさんある
スマホを持たせるリスクは多く語られるけど、素晴らしいメリットだってたくさんある!
私はどちらかというと、こちらを重要視しています。
むしろ、今の時代を生きる子どもたちにとって、スマホは「文明の杖」みたいなもの。

メリットを知ったうえで上手に活用できるようになったら、それこそ
子どもの世界を大きく広げるチャンスになると思います!
たとえば・・・
- 家族や友達とすぐに連絡が取れる(防犯・安全対策)
LINE、Google・ファミリーリンクのGPS機能、フル活用!!
- 知りたいことをすぐに調べられる
スマホに限らずPCでも、インターネットの使い方は今後のIT時代において必須スキル!
- 趣味や興味の幅が広がる(スポーツ、音楽、イラスト、プログラミングなど)
娘はYoutubeでスポーツの習い事の練習方法を検索して学んでいます。
他にも発表会で弾く曲のイメージを聞いたりなど、色々活用中。
- 情報リテラシーを高めることができる
「情報を見極め、適切に判断する力」、すなわち「情報社会を賢く生きる力」のこと。
早い段階でデジタル社会に慣れることができます。
持たないことのデメリットもちゃんと理解しておく
- 緊急時の連絡手段が限られる
子どもが外出先でトラブルに巻き込まれた時、すぐに親に連絡できないリスクがあります。
公衆電話って・・・どこよ?って時代になってます、はい。
- 友達とのコミュニケーションに遅れが出る
LINEグループやクラス連絡網がスマホ前提になっている地域も!?
置いてきぼり感を抱きやすくなることもあります。
我が家には固定電話がないので、娘が友達と連絡を取り合う手段はLINE一択。
明日の宿題の確認をしたり、放課後遊びに行く約束など、もうなくては困るレベル。
- 情報リテラシーを学ぶ機会を逃す
スマホを適切に使う力(=デジタルリテラシー)は小さいうちから経験を積まないと身につきにくいようです。
持たせない=守る、だkぇではなく、学ばせる機会も失っているかもしれません。
- 周囲との差を過剰に意識させる
「なんで自分だけ持っていないの?」という思いが、自己肯定感を下げる方向に働くことも。
ここは子どもの性格にもよりますが、思春期は特にデリケートに感じやすいかもしれません。
- GPSや見守り機能を使えない
スマホがあれば、居場所確認や緊急SOS発信など、親子双方の安心材料になります。
持たせない場合は、代わりの手段(キッズケータイ、GPS端末など)を工夫する必要があります。
思春期に入った子どもたちは扱いが難しい・・・

むしろ、中学に入ってから持たせるでは遅い気がしなくもない・・・
なぜなら、その頃には絶賛反抗期になっていることでしょう。
一緒に決めたルールなんかも簡単に破られることでしょう。
親の言うことにどれだけ耳を傾けてくれることだろうか。
親子関係はスマホを通して悪化の一途を辿っていく気がしならない・・・
そう思い、ある程度しっかりしている娘には今のうちにある程度の使い方やマナーを教えるべく
早めに持たせることにしたわけです。
情報(デジタル)リテラシーとは?
先にも述べたように、”ネットの世界を安全に、賢く、生き抜く力”です。
- 情報の正しさを見抜く力
- 個人情報を守る意識
- フェイクニュースや詐欺から自分を守る判断力
- SNSでのマナーや思いやり
こうやって並べてみると…
学校ではあまり教えてくれないのに、実はめちゃくちゃ重要じゃん!と思われることばかり。
大人でさえ詐欺に簡単に遭ってしまう世の中で、これからを生きる子どもたちが無知でいいわけがありません。

スマホをもたせることは、デジタルの海に小さな船を浮かべるようなもの。
だからこそ、漕ぎ方(=デジタルリテラシー)を一緒に教える必要があるのです。
我が家では毎日、テレビで流れる怖いニュースを見ながら
「こういう使い方するから怖い事件に遭っちゃったんだね〜」
と、半ば脅しで(笑)教えています。
毎日少しずつですが、教えていくと、こうすると怖いことが起こる、ネットの向こう側に怖い人がいっぱいいるということを
子どもながらに学んでいるのを実感します。
まとめ:親子で話し合って着地点を探そう
持たせる、持たせないは各家庭でメリット・デメリットをきちんと理解したうえで話し合い、決めること。
家庭に合った着地点を探ることが大切だと思います。
わたしとしては、持たせない選択は悪くないけれど”ゼロリスク”ではないということを強く感じるわけです。
そして、スマホデビューはゴールではありません。
親子で一緒に育っていくためのスタートラインと捉えた方が良さそうです。
その子に合ったタイミングで、自分の家庭に合った方法で、一歩を踏み出せばいいのです。
ちなみに我が家のスマホ代は一人1500円以下!
3台で持っていても5000円でお釣りがもらえます。
子どものスマホデビューを機に、スマホの料金を見直してみるのもアリかも!



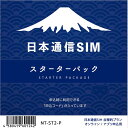


コメント